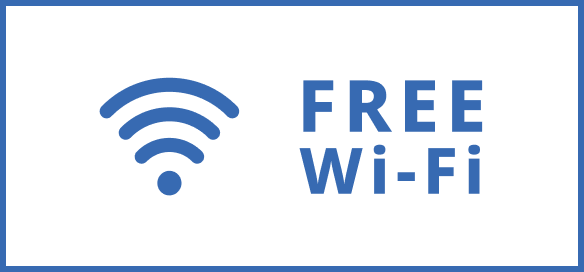歯ぎしり
目次
歯ぎしりとは?
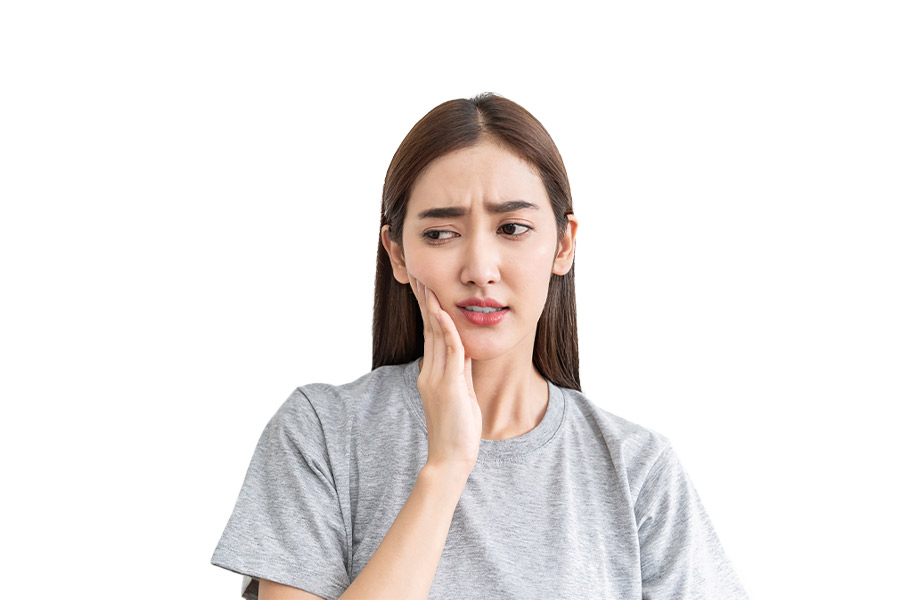
歯ぎしりとは、睡眠中や無意識の状態で上下の歯を強くこすり合わせたり、食いしばる動作を指します。
ストレスやかみ合わせの問題が主な原因で、歯の摩耗や顎の痛み、頭痛などを引き起こすことがあります。
歯ぎしりの原因とは?

- ストレスや緊張
心理的ストレスが身体に現れ、無意識に歯ぎしりを引き起こすことがあります。 - かみ合わせの問題
歯や顎の位置がずれると、無意識に調整しようとする動きが生じることがあります。 - 生活習慣や姿勢
過剰なカフェインやアルコールの摂取、悪い姿勢が影響する場合があります。 - 睡眠障害
睡眠時無呼吸症候群などの問題が関係することもあります。 - 遺伝
家族に歯ぎしりの傾向がある場合、遺伝的な要因が関与している可能性があります。
歯ぎしりを放置しておくと
起こる症状とは?

- 歯の摩耗
歯の表面がすり減り、咬み合わせが変化したり、知覚過敏を引き起こすことがあります。 - 歯の破折(ひび割れ・折れる)
強い力が繰り返されることで、歯がひび割れたり欠けるリスクが高まります。 - 詰め物や被せ物の損傷
歯の補綴物(詰め物や被せ物)が破損することがあります。 - 咬合の乱れ
歯ぎしりによる歯の損耗で、かみ合わせのバランスが崩れる場合があります。 - 歯周病の悪化
過剰な力が歯を支える歯周組織に負担をかけ、歯周病の進行を早めることがあります。 - 顎関節症
顎の関節や筋肉に負担がかかり、顎の痛みや音、開口障害などが生じる可能性があります。
歯ぎしりのセルフチェック

セルフチェックポイント
朝起きたときの顎や歯の違和感
顎が疲れている、痛い、硬いと感じる場合は歯ぎしりの可能性があります。
歯のすり減り
鏡で歯をチェックし、歯の先端が平らになっている、または尖った部分がなくなっている場合は、歯ぎしりが疑われます。
歯の痛みや知覚過敏
冷たいものや甘いものがしみる場合、歯ぎしりによるエナメル質の摩耗が原因かもしれません。
頬や舌の内側の傷
無意識に噛んでしまい、頬や舌の内側に傷がついていることがあります。
頭痛や首の痛み
朝起きたときに頭痛や首の痛みを感じる場合、歯ぎしりが関係している可能性があります。
周囲の指摘
寝ている間に家族やパートナーから「歯ぎしりの音がうるさい」と言われることがあります。
確信が持てない場合
歯ぎしりは自覚が難しいため、上記のチェックポイントに該当する場合は、歯科医師の診察を受けることをおすすめします。歯の状態や顎の筋肉の緊張を見て、専門的に判断してもらうと良いでしょう。
歯ぎしりの主な症状とは?

歯の摩耗や変形
歯の表面が平らにすり減る、またはエナメル質が削れて知覚過敏になる。
歯のひび割れや破損
強い圧力がかかることで、歯にヒビが入ったり、欠けたりすることがあります。
顎の痛みやこわばり
朝起きたときに顎が疲れている、痛い、または動きにくいと感じる。
頭痛や耳の周りの痛み
特にこめかみ付近の頭痛が頻繁に起こることがあります。顎の筋肉の緊張が原因となることが多いです。
歯肉の痛みや腫れ
歯ぎしりが歯周組織に負担をかけ、炎症や痛みを引き起こす場合があります。
睡眠の質の低下
自分では気づかない場合でも、歯ぎしりによるストレスで眠りが浅くなることがあります。
詰め物や被せ物の損傷
歯ぎしりが原因で歯の補綴物が外れたり、壊れることが多いです。
周囲からの指摘
寝ている間に歯ぎしりの音が大きいと家族やパートナーに指摘される場合があります。
歯の噛みしめ
(クレンチング)とは?

歯の噛みしめ(クレンチング)の症状は、歯ぎしり(グラインディング)と似ていますが、以下のような特徴があります。
クレンチングは歯を強くかみ合わせる動作で、顎や歯、周囲の組織に負担をかけます。
主な症状
顎の痛みやこわばり
特に朝起きたときや、日中に集中しているときに、顎が疲れて痛むことがあります。
頭痛やこめかみの痛み
顎を動かす筋肉が緊張し、頭痛やこめかみ周辺の違和感を引き起こします。
歯の痛みや知覚過敏
持続的な圧力が歯にかかるため、歯の内部の神経が刺激されて痛みやしみる感覚が出ることがあります。
歯の摩耗やひび割れ
歯ぎしりほどではありませんが、歯のかみ合わせ部分が摩耗したり、ひびが入ることがあります。
歯肉や歯周組織の負担
歯茎が痛む、歯が動揺する、歯周病が悪化するなどの症状が現れる場合があります。
顎関節症のリスク
長時間の噛みしめが顎関節に負担をかけ、顎関節症を引き起こすことがあります。
クリック音や開口障害が伴うこともあります。
肩こりや首の痛み
顎の筋肉が緊張すると、首や肩の筋肉にも影響を及ぼし、慢性的な痛みや凝りを感じることがあります。
クレンチング特有の傾向
- 日中、集中しているとき(仕事やスマホ使用中など)に無意識で発生することが多いです。
- 睡眠中の無意識な行動もあり、ナイトガードなどの対応が必要になる場合があります。
歯を鳴らす
「タッピング」とは?

歯を鳴らす行為、いわゆるタッピング(Tapping)は、上下の歯を軽く接触させてカチカチと音を鳴らす行動を指します。この行動も、顎や歯に影響を及ぼす場合があります。以下にタッピングの主な症状を挙げます。
タッピングの主な症状
歯の表面の摩耗
繰り返し歯を接触させることで、エナメル質がわずかに削れ、長期間続くと歯の摩耗が進むことがあります。
歯のひび割れ
硬いものに歯をぶつけるような動きが続くと、歯に小さなひびが入る可能性があります。
歯肉の炎症や負担
歯茎や歯の支えとなる歯周組織に負担をかけ、炎症や腫れが起こることがあります。
顎の疲れや筋肉のこわばり
タッピングを頻繁に行うことで、顎の筋肉が過剰に使われ、疲労やこわばりを感じることがあります。
音に起因する心理的ストレス
無意識にタッピングを行う場合、自分や周囲が音を気にしてストレスを感じることがあります。
歯や補綴物の損傷
被せ物や詰め物がある場合、それらが外れたり割れたりするリスクが高まります。
タッピングの傾向と注意点
- タッピングは、集中しているときや緊張状態のときに無意識に行われることが多いです。
- 歯ぎしりや噛みしめと同じく、ストレスやかみ合わせの問題が原因となることがあります。
タッピングが長期間続く場合は、歯科医に相談し、ナイトガードやストレス対策を検討することをおすすめします。また、原因がかみ合わせにある場合は、適切な調整が必要になることもあります。
歯ぎしりの
治療方法について

歯ぎしりに対する治療は、症状の程度や原因に応じて異なります。以下に一般的な治療法を挙げます。
マウスピース(ナイトガード)
装着
- 就寝中の歯ぎしりを防ぎ、歯や顎への負担を軽減するために使用されます。歯科医院で患者の歯型に合わせたカスタムマウスピースを作ることで、より効果的な保護が可能です。
かみ合わせの調整
- かみ合わせに問題がある場合、歯科医が歯を削るなどして調整を行います。また、詰め物や被せ物が原因であれば、適切に修正します。
ストレス管理
- ストレスが主な原因と考えられる場合、リラクゼーション法(深呼吸、ヨガ、マインドフルネスなど)やカウンセリングを行うことで症状が軽減することがあります。
行動療法
- 日中に無意識で歯ぎしりをしている場合、意識的に習慣を修正するトレーニングが行われます。これには、歯を離したリラックスした状態を保つ練習などが含まれます。
薬物療法
- 重度の歯ぎしりや顎の痛みを伴う場合、痛みを和らげるための鎮痛剤や、筋肉の緊張を緩和する筋弛緩薬が処方されることがあります。
- 睡眠障害が原因の場合は、睡眠改善薬が使用されることもあります。
ライフスタイルの改善
- カフェインやアルコールの摂取を減らし、十分な睡眠を取ることで、歯ぎしりの頻度を減らすことができます。
歯ぎしりの治療の
初診から治療開始後の流れ
治療の第一歩は、歯ぎしりの原因を特定することです。
原因がわかれば、適切な治療法を選択でき、症状の進行を防ぐことが可能です。
継続的なケアが重要ですので、定期的なチェックアップを受けることもおすすめします。
一般的な流れをご説明します。
問診
現在の症状について、歯ぎしりについての自覚、既往歴、家族歴をお聞きします。

症状の確認
どのような症状がいつから、どれぐらいあるのかの確認をします。

口腔内の診査
歯ぎしりによって口腔内に現れる症状を確認します。

口腔外の検査
同じく口腔外に現れる症状を確認します。

レントゲン、CTによる診査
場合によってレントゲン撮影を行い歯並び、むし歯、歯周組織、顎関節、かみ合わせの確認をします。

かみ合わせの確認
口の中でかみ合わせを確認します。
また顎の動きもチェックします。

顎の動きの診査
歯の型を取り、口の中ではなかなかわからない実際のかみ合わせや顎の動きを調べるため咬合器という機器を使って診査します。

最終診断・治療開始
以上のデータをもとに診断し、治療に移ります。




 0228-38-2266
0228-38-2266